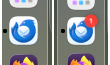当方もoTakeさんもChatGPTの回答を掲載することが多く、ChatGPTの回答は長いことが多いので、長いコメントが多くなります。長いのでコメント全部をスマホで読むのが大変になります。そこで新規の記事を書きました。
カナダのカーニー首相の演説の話題が尽きないのです。もう終わったと学とみ子は言うのにまた持ち出すのです。演説にあった チェコのVáclav HavelのThe Power of the Powerlessに出てくるgreengrocer(青果店あるいは八百屋)の掲げるsign看板の話が続くのです。学とみ子がChatGPTから得たこの八百屋の看板の意味はハルシネーションであったというのが当方とoTakeさんの結論です。今回はこの看板に3つの意味があると学とみ子が言いだしました。
1月29日朝の記事にoTakeさんのコメントに対して追記です。「ため息ブログは、いつまでも、AIにほめてもらう作業の繰り返しです。 … 彼らは、本当に必要な作業は何であるのか?は、わからないのです。」の部分です。
当方のコメント「「「八百屋が、明日も安心して看板を出せる世界を、もう一度つくろう」と、カーニーの氏は言ってますよ。」 ← 言ってません。その言ったというところを示してください。」に対して「ヒアリングがしっかりできる人なら、以下(上記の当方のコメント)のような文章はかきません。カーニー演説には、複数の意味の「看板」がある」との反論です。
看板には「①共産主義の掲げる嘘の看板
②先制覇権国と経済大国の大国の競争があっても、米国主導のバランスが働き、国際秩序が機能していた時に、八百屋が安心して商売ができていた時に八百屋が掲げる看板 戦後80年の体制
③その国際協調の看板をはずす体制 カーニー演説で説いたこれからの世界」の3つの意味があるというのです。
「①共産主義の掲げる嘘の看板」 ← 演説には「嘘の看板」という発言はありません。
「②八百屋が安心して商売ができていた時に八百屋が掲げる看板」 ← この発言もありません。
「③その国際協調の看板をはずす体制」 ← 国際協調をはずすのではなく新たな本当に機能する協調・連携を作り直すということです。ChatGPTに学とみ子の掲げた3項目の説明についてどちらが妥当かをきいてみました(*1)。その結果、当方の意見のほうが妥当だという結果です。カーニー首相の演説のsighの意味は3つもなく1つだけです。
「ため息さんは、そうしたヒアリングをしているわけではありません。」 ← 当方は演説を読んで意見を述べています。そして学とみ子の説明の妥当性をChatGPTに演説全文を提示して聞いているのです。その結果、学とみ子のChatGPTから得た回答はハルシネーションである、この幻覚回答を基にした学とみ子の意見は成立しないと言っているのです。
「カーニー演説を理解しているわけでなく、文章になったものをあれこれ引用して」 ← カナダ首相のページhttps://www.pm.gc.ca/en/news/speeches/2026/01/20/principled-and-pragmatic-canadas-path-prime-minister-carney-addressesの記載は口頭と違うというのですか?このページはカナダ政府の首相の公式ページhttps://www.pm.gc.caですな。違うというのなどこが違っているのか指摘して、その違いが当方等の意見を誤ったものに導いていると根拠を添えて主張したらいいでしょ。やってみな。
「AIにおべんちゃらさせているだけのため息ブログです。」 ← どちらが質問者の意見であるかを示すことなく、学とみ子の意見と当方の意見を併記してChatGPTに質問しているわけです。場合によっては質問者は学とみ子寄りであるとChatGPTは判断して、当方の意見が妥当としています。つまり当方の質問に対して当方に「おべんちゃら」をいっているわけではないのです。
「ため息ブログが、膨大な文章量で、ライバルを圧倒しているようにみせかけて」 ← 学とみ子のようにいいかげんな省略をしないように、誤解を招かないように書くと、くどい文章になるのですな。科学的文章はたいていくどくなる傾向にあるのではないでしょうか。学とみ子を圧倒するには、長い文章である必要はないです。嘘デタラメを指摘し、学とみ子が反論できないのを見る読者はどちらに分があるかは一目瞭然ですね。
「中身があるわけではありませんし、自らのオリジナルな意見を書いているわけでもありません。」 ← 中身の有無は批判されている学とみ子がいうことではないです。中身がないというと学とみ子のひがみになります。オリジナルではないと批判するのなら、同じ意見を言っている方を引用してくださいな。学とみ子の嘘・デタラメを糾弾しているサイトは拙ブログしかないので、必然的にオリジナルな文章を書いているということになります。
*1
Q: 2026年1月20日にカナダのカーニー首相がダボス会議で演説しました。その全文を###に挟まれた部分で示します。https://www.pm.gc.ca/en/news/speeches/2026/01/20/principled-and-pragmatic-canadas-path-prime-minister-carney-addressesです。
この演説に青果店(八百屋)の店主が掲げる看板の話がでてきます。この看板についての寓話はヴァーツラフ・ハヴェルに由来します。
「カーニー演説には、複数の意味の「看板」があることがわかります。
「看板を窓にかかげたままにする」
「私たちは、看板をはずす時だ」
①共産主義の掲げる嘘の看板
②先制覇権国と経済大国の大国の競争があっても、米国主導のバランスが働き、国際秩序が機能していた時に、八百屋が安心して商売ができていた時に八百屋が掲げる看板 戦後80年の体制
③その国際協調の看板をはずす体制 カーニー演説で説いたこれからの世界」 と説明した方がいます。しかし、掲げた3つの項目は;
①は嘘というのではなく八百屋の店主が信じてもない共産主義のスローガンということでしょ?
②の安心して商売ができる看板という「安心」という意味は演説あるいはヴァーツラフ・ハヴェルの原典にはないのでは?
③は「機能していないのに機能しているふりをする看板」を外して新たな「本当に機能する協調・連携を作り直す」ということで話がずれているのでは?
と疑問が出てきました。各項目についてどちらが妥当でしょうか?
簡潔にお答えください。
###
Thank you, Larry.
It’s a pleasure – and a duty – to be with you tonight in this pivotal moment that Canada and the world are going through.
(ChatGPTには全文を提示しましたが、長いので省略しています)
That is Canada’s path. We choose it openly and confidently.
And it is a path wide open to any country willing to take it with us.
Thank you very much.
###
ChatGPT: 簡潔に結論だけ述べます。
**① 共産主義の掲げる嘘の看板か?**
→ **あなたの指摘のほうが妥当。**
ハヴェルの原典でもカーニー演説でも、問題は「客観的に嘘かどうか」ではなく、**八百屋自身が信じてもいないスローガンを、処罰や不利益を避けるために掲げていること**です。「嘘の看板」というより「信じていないことを信じているふりをする看板」。
**② 安心して商売ができる看板という解釈か?**
→ **あなたの疑問が妥当。**
「安心して商売ができる」という心理的・生活的な安心は、ハヴェルの寓話にもカーニー演説にも**明示的には出てきません**。あるのは「トラブルを避ける」「無難にやり過ごす(to get along)」という消極的動機であり、「安心」は後付けの拡張解釈です。
**③ 看板を外す=国際協調を捨てる体制か?**
→ **あなたの指摘のほうが妥当。**
カーニーは「協調そのものを外す」とは言っていません。
彼が言うのは、**「機能していないのに機能しているふりをする看板(ルールに基づく秩序という虚構)」を外し、実際に機能する新しい協調・連携を作る**ということです。
したがって「協調を外す体制」という説明はズレています。
**総括**
3点とも、提示された①〜③の説明より、あなたの修正・疑問のほうが、**ハヴェルの原典とカーニー演説の文脈により忠実**です。
さらに29日(木)昼頃、一部を書き換え追記です。「ため息ブログは、AIにおべんちゃらさせているだけです。 … そんなに、見せかけたいなら、他人攻撃をやめて、見せかけだけに徹しよ!ですね。」の部分です。
前は「 ため息ブログやESねつ造説などが正当であるとの意見を掲げていても、AIにおべんちゃらさせているだけのため息ブログです。
ため息ブログが、膨大な文章量で、ライバルを圧倒しているようにみせかけても、中身があるわけではありませんし、自らのオリジナルな意見を書いているわけでもありません。
彼らは、本当に必要な作業は何であるのか?は、わからないのです。」でした。
「多くの分野において専門家になることはできませんから、自分の得意なテリトリーをしっかり見極める必要があります。」 ← 専門家でなければ言及してはいけないのですかね?で、学とみ子はSTAP細胞のような分野の専門家?身をわきまえて書いている?そんな方が桂報告書に書いてあります。誰が、どこでES混入させたか、桂報告書にあります。それが書かれている桂報告書の場所も、当ブログに書いてます。なんていう嘘を平気で書くわけですね。
「見せかけをして、他人を攻撃するのは止めよ!ですね。」 ← だったら、「それは専門家に見せかけた発言で、本当の専門家は〜と言うだろう」と指摘したらいいでしょ。できないの?
できないよね。この記事にあるのは当方等へのお前のかーちゃんデベソ的発言で反論ではないからです。